生活習慣病保険は、がん・心疾患・脳血管疾患などに備える手段のひとつですが、中にはいらないと考えて加入を見送る人も少なくありません。
その理由は「公的医療保険である程度の医療費はカバーされる」「保険金・給付金が支払われないケースがある」などさまざまです。
生活習慣病を保障する保険の内容や、いらないと言われる主な理由などを解説します。ご自身にとって生活習慣病保険が必要かどうか悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
生活習慣病とは?
生活習慣病は、食事、運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が発症や進行に関係する病気の総称です。
ひと昔前は「成人病」と呼ばれていましたが、加齢だけでなく生活習慣も大きく影響することが分かったため、1996年頃からは「生活習慣病」という名称が一般的になりました。
生活習慣病に該当する主な病気と総患者数の近年の推移は以下のとおりです。
| 生活習慣病に該当する主な病気と総患者数の近年の推移(単位:万人) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平成26年 | 平成29年 | 令和2年 | 令和5年 | |
| がん(悪性新生物) | 30.08 | 30.98 | 29.51 | 29.25 |
| 糖尿病 | 24.33 | 24.29 | 23.03 | 21.81 |
| 高血圧性疾患 | 67.78 | 65.25 | 59.88 | 61.06 |
| 虚血性心疾患(急性心筋梗塞・狭心症など) | 7.5 | 7.07 | 6.52 | 6.27 |
| 脳血管疾患(脳卒中など) | 25.34 | 23.19 | 19.75 | 18.43 |
| 肝疾患(肝硬変など) | 4.06 | 3.43 | 3.1 | 2.86 |
| 腎尿路生殖器系の疾患(慢性腎不全など) | 33 | 37.18 | 35.58 | 38.82 |
※上記には生活習慣病とは呼ばれない疾病の患者数も含まれています
多くの生活習慣病は、患者数が少しずつ減少している一方で、がんは約30万人、高血圧性疾患は約60万人もの患者がいます。
生活習慣病は、誰にでも発症するリスクがあるだけでなく自覚症状がないまま進行するケースも多いです。
また、ひとたび発症すると治療が長期化しやすい点も主な特徴です。高血圧や糖尿病のように、完治が難しく長い付き合いとなる病気もあります。
生活習慣病を含む「三大疾病」「七大疾病」とは?
生活習慣病のうち、死亡リスクが高いといわれるがん(悪性新生物)や心疾患(心筋梗塞・狭心症など)、脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)は「三大疾病」と呼ばれます。
また、三大疾病に加えて糖尿病、高血圧性疾患、肝硬変、慢性腎不全は「七大疾病」と呼ばれることがあります。
特に、糖尿病や高血圧などは、動脈硬化を進行させ心疾患や脳血管疾患の発症につながるといわれています。
生活習慣病に備える保険
生活習慣病に備えられる保険には、以下のような種類があります。
特定疾病保険(三大疾病保険など)

特定疾病保険は、がん・心筋梗塞・脳卒中といった特定の疾病を保障する保険です。
被保険者(保険の対象となる人)が契約後に初めてがんと診断されたときや、心疾患または脳血管疾患で所定の状態に該当したときなどに、特定疾病保険金が支払われます。
保険会社によっては七大疾病や八大疾病で所定の状態になったときに保険金が支払われる商品を取り扱っています。
特定疾病保険金は200万円や300万円などまとまった金額であるのが一般的であり、使い道に制限はありません。
そのため、治療費や交通費、生活費などの支払いに充てられるだけでなく、働けないことによる収入の減少分をカバーすることも可能です。
また、特定疾病保険金を受け取ることなく被保険者が死亡した場合は、死亡保険金が支払われます。死亡保険金と特定疾病保険金は同額です。
特定疾病保険金を受け取るためには、保険会社が定める支払要件に該当する必要があります。支払要件の例は以下のとおりです。
| 特定疾病保険の支払要件の一例 | ||
|---|---|---|
| 支払要件 | ||
| がん(悪性新生物) | ・契約後に生まれて初めてがんと医師によって診断確定されたとき※上皮内がん、皮膚がんは除く | |
| 急性心筋梗塞 | ・契約後に急性心筋梗塞になり、医師の診断を受けた初診日から60日以上労働が制限される状態が継続したと医師によって診断されたとき※狭心症は対象外 | |
| 脳卒中 | ・契約後に脳卒中になり、医師の診療を受けた初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき | |
特定疾病保険金の支払要件は保険会社によって異なります。
特定疾病保険を検討する際は、契約のしおりや約款、パンフレットなどをよく読み、保障対象となる疾病や支払要件をよく確認することが大切です。
医療保険


民間医療保険は、病気やケガによる入院・手術に備えられる保険です。
医療保険の基本的な保障は、病気やケガの治療を目的とした入院をしたときの「入院給付金」と、所定の手術を受けたときの「手術給付金」です。
また、特約を付けることで保障を手厚くすることも可能です。
保険会社の多くは、三大疾病や七大疾病などで所定の状態に該当するとまとまった金額の給付金を受け取れる特約を、医療保険に付加することができます。
入院給付金には、給付金の支払対象となる入院日数に上限が設けられているのが一般的ですが、三大疾病や七大疾病などに該当すると無制限となる商品もあります。
がん保険


がん保険は、がんに手厚く備えられる保険です。がんと診断確定されたときの「がん診断一時金」や、手術や放射線治療、抗がん剤治療などを受けた月ごとに支払われる「がん治療給付金」などが主な保障です。
がん診断一時金は、生まれて初めてのがんと診断されたときに1回のみ支払われるのが一般的でした。しかし、近年は「1年につき1回まで」などを限度に複数回支払われるものも増えてきているため、再発・転移に備えることも可能です。
保障対象となるがんは、基本的に悪性新生物を指しますが、商品によってはがん細胞が組織の表面を覆う上皮内にとどまる上皮内新生物(上皮内がん)が含まれます。
ただし、がん保険で保障されるのは基本的にがんのみであり、心疾患や脳血管疾患は保障対象外です。
また、がん保険には免責期間が設けられており、多くの場合保障が始まってから90日(または3か月)のあいだに診断されたがんは保障されません。
生活習慣病保険がいらないと言われる理由
生活習慣病に備えられる保険がいらないと言われる主な理由は以下のとおりです。
医療費の自己負担は最大3割で済むから
日本は国民皆保険が導入されており、国民の全員に公的医療保険の加入が義務づけられています。
公的医療保険とは、会社員や公務員が加入する健康保険や、自営業やフリーランスを対象とした国民健康保険などのことです。
公的医療保険に加入している人は、病院やクリニックなどの支払窓口に健康保険証を提示すると、自己負担が実際にかかった医療費の最大3割で済みます。
そのため、生活習慣病になったときの医療費は貯蓄で賄えると考えて保険の加入を見送る人は少なくありません。
高額療養費制度があるから

高額療養費制度は、1か月(その月の1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。
ひと月あたりの自己負担上限額は主に年収と年齢によって決まります。69歳以下の方の自己負担上限額は以下のとおりです。
| 高額療養費制度の自己負担上限額(69歳以下の場合) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所得区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |||
| ア | 年収約1,160万円〜健保:標報83万円以上国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(総医療費−842,000)×1% | ||
| イ | 年収約770万〜約1,160万円健保:標報53〜79万円国保:旧ただし書き所得600万〜901万円 | 167,400円+(総医療費−558,000)×1% | ||
| ウ | 年収約370万〜約770万円健保:標報28〜50万円国保:旧ただし書き所得210万〜600万円 | 80,100円+(医療費−267,000)×1% | ||
| エ | 〜年収約370万円健保:標報26万円以下国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 | ||
| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | ||
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
また、自己負担限度額を超える負担額を支払った回数が過去12か月間に3回以上ある場合は、4回目から「多数回該当」が適用され、上限額がさらに引き下げられます。
たとえ生活習慣病で多額の医療費が発生したとしても、高額療養費を適用することで実際に負担する金額は抑えられるため、民間の保険で備える必要性は低いと考える人もいます。
加入しても保険金や給付金を受け取れるとは限らない
生活習慣病を保障する保険は、給付金の支払要件が定められており、単に診断を受けただけでは保険金や給付金を受け取れない場合があります。
たとえば、心疾患の場合は「1日以上の入院をしたときまたは所定の手術を受けたとき」「初診日から60日以上働けない状態が継続したと医師に診断されたとき」といった支払要件を満たす必要があります。
糖尿病の場合は「治療のためにインスリン治療を継続して180日以上受けたとき」といったような要件が設定されるのが一般的です。
支払要件を満たしていない場合や保障範囲に含まれていない生活習慣病にかかった場合、給付金は受け取れません。
また、がんに関する保障には通常90日(または3か月)程度の免責期間があり、免責期間中に診断されたがんは保障対象外です。
保険に加入したにもかかわらず、生活習慣病になったときに何も受け取れないこともあるため、「それなら最初から加入しないほうが良い」と考える人もいます。
高齢で加入すると保険料が高くなるから
生命保険や医療保険などは、加入する時点での年齢が高いほど病気になるリスクが上昇するため、保険料は高額になるのが一般的です。
生活習慣病が心配な年齢になり、万が一に備えるために保険の加入を検討したときには、保険料が高額になっていることがあります。
また、70〜74歳で一般的な所得の人の医療費自己負担は2割です。75歳以上の人はさらに軽減され、一般的な所得者であれば1割、一定の所得がある人は2割負担となります。
※70歳以上で現役並みの所得がある人は3割負担
以上の点から「高い保険料を支払うよりも、貯蓄で備えたほうが合理的ではないか」と考え、生活習慣病を保障する保険の加入を見送る人もいるようです。
若いうちは生活習慣病になるリスクが低いから
若い世代は、病気やケガのリスクが相対的に低いため、特定疾病保険や医療保険などに割安な保険料で加入できます。
一方、高齢者と比較して生活習慣病にかかりにくいため、保険に加入する必要性を感じない方も多くいます。
生命保険文化センターの「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、2人以上世帯の場合、生命保険に加入しない理由として「現時点では必要性をあまり感じない」と回答した人の割合は、以下のとおりです。
- 29歳以下:46.9%
- 30〜34歳:36.1%
- 35〜39歳:26.2%
- 40~44歳:26.4%
- 45~49歳:30.0%
- 50~54歳:28.1%
- 55~59歳:43.5%
- 60~64歳:41.2%
- 65~69歳:33.3%
- 70~74歳:28.6%
- 75~79歳:30.0%
- 80~84歳:33.3%
- 85~89歳:33.3%
- 90歳以上:16.7%
参照:2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2人以上世帯)|生命保険文化センター
たとえ割安な保険料で加入できるとしても、まだ若く生活習慣病のリスクは低いため、給付金を受け取る機会はないだろうと考える人も一定数いるのが実情です。
生活習慣の改善で予防できるから
生活習慣病は、バランスの取れた食事や適度な運動習慣、禁煙、節酒などを心がけ、十分な睡眠を取ることで、発症リスクを低減できる可能性があります。
「保険料を支払うよりも、健康的な食生活や運動、定期的な検診などの予防にお金を使いたい」と考えて保険の加入を見送る人もいます。
生活習慣病保険の必要性
生活習慣病を保障する保険はさまざまな理由から加入する必要はないと言われる一方で、すべての人にとって不要というわけではありません。
特定疾病保険や医療保険などの必要性を解説します。
三大疾病は日本人の死因の上位
三大疾病であるがん、心疾患、脳血管疾患は、長らく日本人の死因上位を占めています。
厚生労働省の「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、2023年の死因のうち、がん、心疾患、脳血管疾患が占める割合はそれぞれ以下のとおりでした。
- がん(悪性新生物<腫瘍>):24.3%
- 心疾患(高血圧性を除く):14.7%
- 脳血管疾患:6.6%
上記を合計すると45.6%であり、三大疾病のみで死因の半数近くを占めています。
死因の多くを占めているということは、これらの病気に罹患すると治療が長引いたり、治療費が多くかかったり、働けなくなったりする場合も多いということです。
だからこそ、生活習慣病と診断されて治療が必要になった時点で、治療費や生活費などを賄えるだけの保障を確保することは非常に重要といえます。
入院が長期化する可能性がある
厚生労働省の「令和5年(2023)患者調査の概況」によると、三大疾病の平均入院日数(在院日数)は以下のとおりです。
- がん(悪性新生物<腫瘍>):14.4日
- 心疾患(高血圧性のものを除く):18.3日
- 脳血管疾患:68.9日
- 糖尿病:31.8日
- 高血圧性疾患:41.6日
- 肝硬変(肝疾患):22.3日
- 慢性腎不全(慢性腎臓病):57.3日
とくに脳血管疾患の平均入院日数は2か月を超えており、精神疾患やアルツハイマー病に次いで長くなっています。
入院が長引けば、それだけ医療費の自己負担額は増えます。公的医療保険の給付対象とならない差額ベッド代や食事代、見舞いに訪れる家族の交通費などもかさんでいくでしょう。
また、働けない期間が長くなって、収入が減少してしまうことも考えられます。
会社員や公務員など健康保険に加入している人は、病気やケガにより4日以上働けなくなった場合に「傷病手当金」を受給することが可能です。
しかし受給額は、過去1年間で受け取った平均給与の約2/3であるため、収入の全額がカバーされるわけではありません。
治療の長期化による経済的な負担を軽減するために、保険に加入して生活習慣病に備えるのもひとつの方法です。
公的医療保険の給付対象外となる費用がある
公的医療保険で生活習慣病を治療する際に支払う費用のすべてがカバーされるわけではありません。以下のような費用は、公的医療保険の給付対象外であり全額自己負担となります。
- 先進医療の技術料
- 自由診療にかかる費用
- 入院時の差額ベッド代
- 入院中の食事代
- リネン類のレンタル料
- 通院や見舞いの際の交通費 など
先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養のことです。先進医療の技術料は全額自己負担であり、高額になる場合があります。
たとえば、がん治療に用いられる陽子線治療の技術料は約267.9万円、重粒子線治療は314.5万円程度かかるとされています。
参照:第138回先進医療会議 【先進医療A】令和6年6月30日時点における先進医療に係る費用|厚生労働省
自由診療は、保険適用外の治療や薬剤を用いる診療です。患者申出療養制度を利用すれば、保険適用部分の医療費は最大3割負担となりますが、適用外である自由診療の部分は、全額自己負担のままです。
生活習慣病の治療においては、公的医療保険だけではカバーしきれない高額な費用が発生する可能性があります。
そのため、万が一に備えて特定疾病保険や民間の医療保険などに加入して備えておくことも検討したほうがよいでしょう。
生活習慣病保険が不要な人の特徴
生活習慣病を保障する保険が不要と考えられる人の例は以下のとおりです。
貯蓄で備えられる人
生活習慣病の治療費や交通費などの支払いや収入の減少に対応できるだけのまとまった貯蓄がある人は、生活習慣病を保障する保険に加入する必要性は低いでしょう。
生活資金や将来のライフイベント(子どもの進学やマイホーム購入など)に必要となる資金の他にも数百万〜数千万円の余剰資金があれば、保険は不要な可能性があります。
公的保障が充実している人
公的医療保険はさまざまな団体が運営をしており、加入先によって給付内容が一部異なる場合があります。
大企業の従業員等が加入する健康保険組合(健保組合)や公務員向けの共済組合では、独自の「付加給付」を設けていることがあります。
付加給付は、ひと月の医療費自己負担額が2万円や3万円などの一定金額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。
付加給付の自己負担上限額は、高額療養費制度よりも低く設定されるのが一般的です。
生活習慣病によって高額な医療費が生じたとしても付加給付を受けられることで自己負担が少なくなる場合、保険に加入する必要性は低いかもしれません。
生活習慣病保険を検討する際は、所属する組合のWebサイトなどで、付加給付の有無や給付内容を確認することが大切です。
生活習慣病を保障する保険に加入するメリット・デメリット
生活習慣病を保障する保険に加入すべきか判断するときは、メリットとデメリットをよく理解することが大切です。主なメリットとデメリットは以下のとおりです。
| 生活習慣病を保障する保険に加入するメリット・デメリット | |
|---|---|
| メリット | デメリット |
| ・生活習慣病に罹患した際のリスクに備えられる ・治療期間の長期化にも備えられる | ・症状が軽い場合には保障が受けられない可能性がある ・生活習慣病のすべてが保障対象ではない |
生活習慣病を保障する保険に加入するメリット
生活習慣病を保障する保険に加入すると、がんや心疾患・脳血管疾患などの場合に給付金を受け取ることができるため、経済的なリスクに備えられます。
とくに特定疾病保険であれば、保険金額を500万円や1,000万円など高額に設定することも可能です。
加入することで「治療に専念するために差額ベッド代を支払って個室に入る」「より高額な費用がかかる治療を受ける」といった選択がしやすくなるでしょう。
また、まとまった金額の給付金を受け取れることに加え、所定の生活習慣病で入院する場合、入院給付金の支払対象となる入院日数が無制限になる商品もあります。
そのため、治療期間が長引いたときの金銭的な負担もカバーできます。
生活習慣病を保障する保険に加入するデメリット
生活習慣病を保障する保険に加入しても、症状が軽い場合には給付金を受け取れない可能性があります。
たとえば、脳血管疾患と診断されても初診日から60日以上、言語障害、運動失調などが続いていないのであれば、給付金の支払対象外になることがあります。
また、保障対象となるのは約款で定められた特定の疾病のみであり、すべての生活習慣病をカバーするわけではありません。生活習慣病といわれる疾病になっても、保険の保障対象に含まれていなければ給付金は支払われません。
特定疾病保険を検討する際は、給付金の支払要件や自身が心配な病気が保障範囲に含まれているかをよく確認することが大切です。
まとめ
生活習慣病を保障する保険に加入すると、がんや心疾患、脳血管疾患など所定の疾病にかかったときに保険金や給付金を受け取ることができます。
商品の仕組みや公的医療保険の給付内容などもよく理解したうえで、自身にとって必要か慎重に判断することが大切です。
とはいえ、必要性を適切に判断するためには、保険や社会保障制度などの専門知識が求められます。加入すべきか判断に迷う場合は、保険の専門知識が豊富なファイナンシャルプランナー(FP)に相談することをおすすめします。
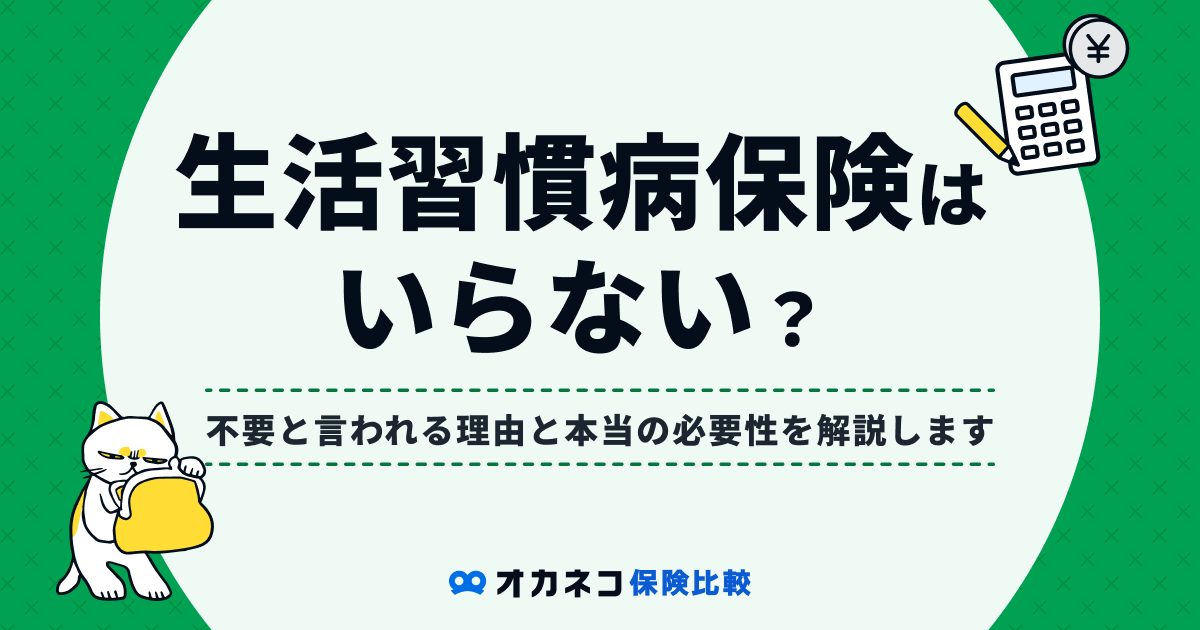

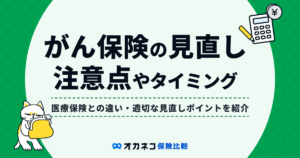
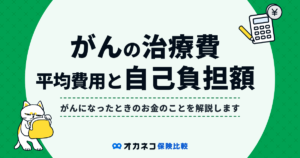
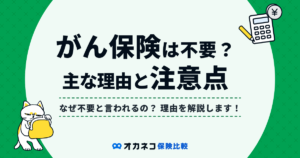
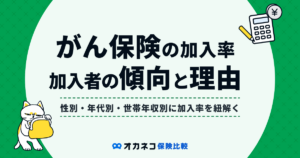
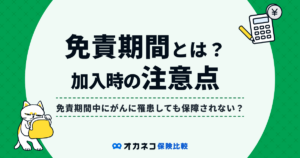
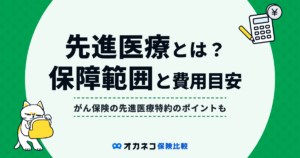
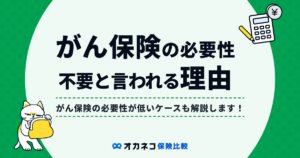
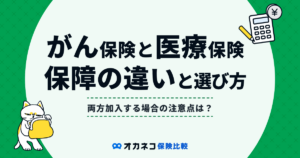
コメント